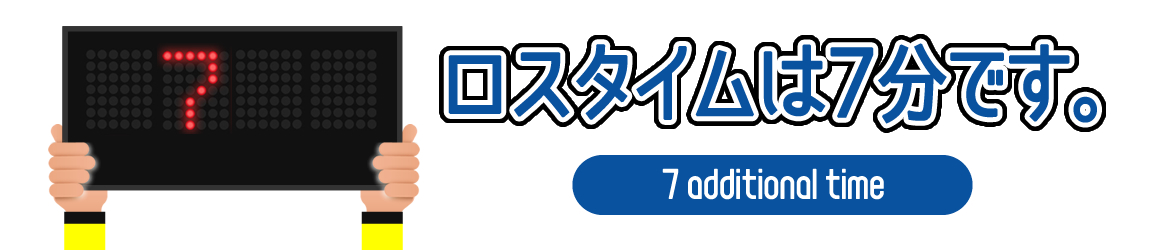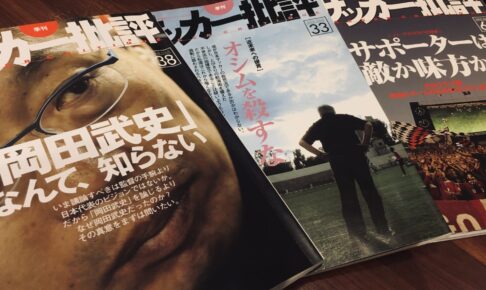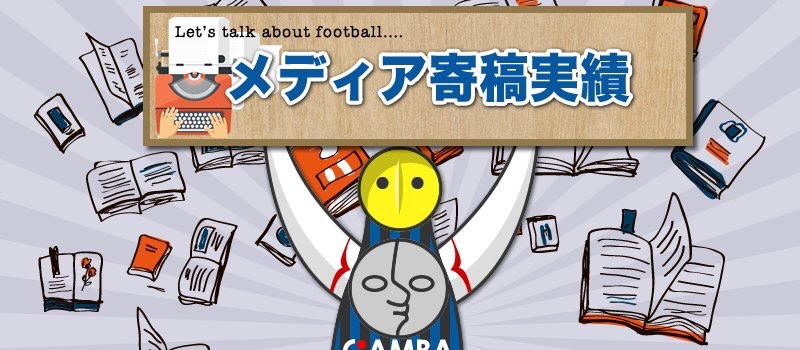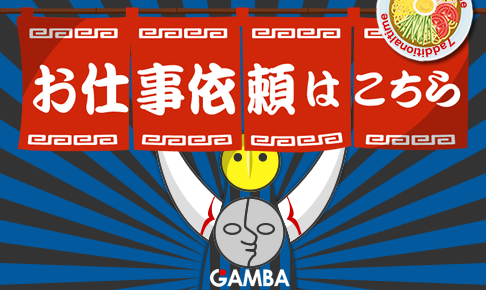5か月ぶりのブログ更新。「文章を書くことはライフワーク」と吹聴していた頃が懐かしい。
《書きたいことがない》
これが正直な気持ちである。より正確に表現すると《長文で》書きたいことがない。X(旧ツイッター)で事足りる。単純なアウトプットで満足。文章を書くことは深く考えること。書きたいことがない自分は思考が単純化している。
なぜこうなった……。
サッカーに関しては法人・個人から連日無数に記事や動画がリリースされる。それは新しいニュースが生まれ続けているからであり、このスポーツの解釈に幅があることの証拠でもある。知らないことだらけ。考察のしがいがあるコンテンツ。それがサッカー。
情報をインプットする習慣は残っている。今春からは時代に逆行して新聞も読んでいる。視野は広がっているはずなのにアウトプットは減っている。
《アテンション・エコノミー》
この影響はある。私がこのブログを始めた2007年当時は「インプレッション」「PV」「フォロワー」なんて言葉はあまり使われていなかった。書きたいから書く。それだけ。
今は違う。嫌でも数字が見えてしまう。長文の投稿は反響を得にくく、「モフレムなんかいい匂いした!にゃふー!!」のようなポストがいいねを集める。結果として「にゃふー」な投稿を増やしてしまうのは人間の性である。にゃふん。

いい匂いがするモフレム
「書きたいことがない」ではなく、「書いても読まれない」が長文を書かなくなった本当の理由なのだろう。自分のことなのに「だろう」と書いたのは認めたくないから。
サポーター仲間が何気なく発した一言を思い出す。
「最近は動画で情報を得られるから活字は読まない」
思考の単純化(言語化の放棄)を迎合的に解釈する自分に情けなさを覚えるが、納得感があることも事実。動画全盛の時代にテキストのニーズは下がっている。
にゃふー!パナスタでアイス食べてモフレムステッカーもらった🍦1番欲しかったやつ当たった🍨 pic.twitter.com/iaq56u0tBA
— ロスタイムは7分です。 (@7additionaltime) May 3, 2025
サッカーが持つ複雑性とアウトプットの単純化。この矛盾とどのように折り合いをつければいいのか。
複雑だからこそ、情報過多だからこそ、シンプルに考えたくなる側面はある。連敗すれば監督解任。アリかナシか。使えるか使えないか。二元論を見聞きする機会が増えた。「ハーフタイムでの修正力は高いが交代の判断が遅い」といった中途半端な意見よりも「無能」と言いきる方が分かりやすい。その方が拡散される。
特にSNSではサポーターミーティングの質疑応答のようなコミュニケーションはもはや普通になっている。過激な主張。複雑さへの無理解。根拠に乏しい更迭論を主張する人が支持を集める。それを憂う人間が少数派になる社会が現実味を帯びてきている。
単純化された情報に触れる度に世界が矮小化されるような気持ちになるが、私にそれを批判する資格はないということ……誰か助けてくれ。
もう声は届かないけれど
長文を書けなくなったもう1つの視点。サッカー観戦の「推し活」化について。
クラブや選手は批評の対象から推しの対象へと変化しつつある。推し活はファン同士のコミュニティ活動も活発なので、仲間の意見(世論)の風向きを見ながらの発信を余儀なくされる。SNSをひらけばエコーチェンバー。盲目的な支持投稿に《互助いいね》をもらって幻の承認欲求を満たす日々。
「推し活」という言語化によって、良くも悪くも他者に自身のアイデンティティを預ける人が増えた。自分(推し)を肯定してくれる記事へのニーズが高まるのは自然なこと。書店のサッカーコーナーに並ぶのは選手の涙と努力の物語。時に批判的な発信が期待される第三者メディアですら軟派な記事を出している。経済合理性を考えれば当然の判断だ。背に腹はかえられない。
共感至上主義のような時代では「分かりやすさ」に価値がある。同じ想いを共有できる人が増えれば熱狂は高まるが、分断も生む。自分と違う意見や批判を受け入れる心のキャパシティが狭まっている。多様性もサッカー観戦の価値を高める要因だったはずなのに。
再びサポーター仲間が発した言葉を引用する。
「昔と比べると(Xの)フォロワーが増えにくくなった」
Xのアルゴリズムには詳しくないが、同じような意見を発信するアカウントでタイムラインが“括られている”ような気はする。新しい意見との出会いが少ないことでフォロワーが増えにくくなっているという仮説。いいねが付かない意見は届かない……いや、同じ人にばかり届いている。
5か月ぶりにブログを更新したのは、そんな社会のトレンドに抵抗したいと思ったから。
私は文章を書いている時間が好きだし、反響の大小に関わらず過去記事すべてが大切だ。自分の分身くらいに捉えている。執筆した記事数に比例してサポーターライフが充実した確信もある。たとえ自分の意見がマイノリティであったとしても。
だから、また書こう。共感はあとでいい。言語化の主導権を取り戻そうと思っている。