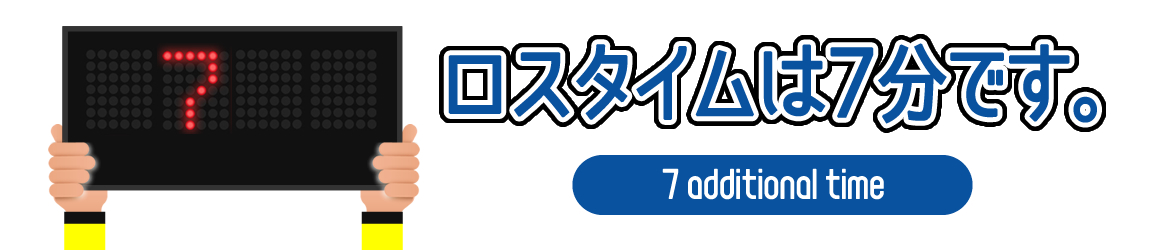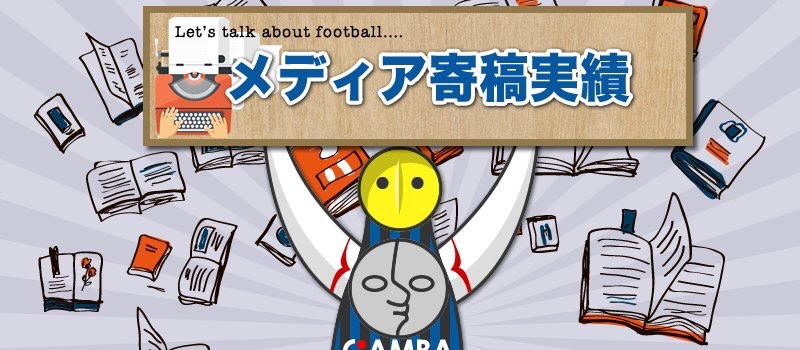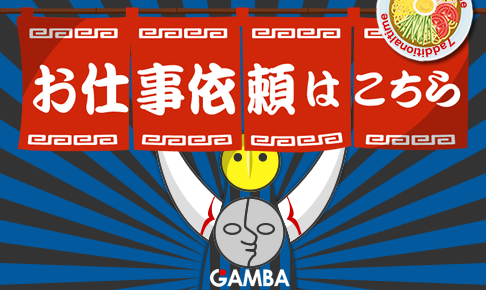今年も残すところ1カ月半。Jリーグは全日程終了を待たずして、来シーズンの人事に関する報道が話題になり始める時期である。私が応援するガンバ大阪の2025シーズン成績は浮き沈みが激しく、順位は中位。チーム全体はもちろん、監督や選手個々に対する評価は分かれるところ。
……と、そんなことを書いていたら、評価する側の松田浩フットボール本部本部長の契約満了が発表された。松田さんには昨年まさに「チームの評価」をテーマにお話を伺っていた。記事内でも本人が語られている通り「中長期的なところに目を向けることの難しさ」をあらためて痛感する人事決定。競技側のトップが変わるということは評価指標も少なからず見直されるだろうし、言わずもがな監督や選手の契約にも影響する。
サッカー界に限らず、評価はあらゆる影響を受けて移ろいやすいものである。「通知簿廃止」「年功序列の再評価」「ティール組織」……最近よく見聞きするニュースも関連した文脈(背景)で解釈している。価値観の多様化が進む時代で自他の評価が合致する難しさは増すばかり。
『VUCA時代』なんて表現される昨今。よく語られる『ガンバらしさ』が永遠に定まらないこと然り。社会情勢をふまえながらトライ&エラーを繰り返し、その時々でなりたい姿を模索し続けるしかないのだろう。チーム強化の定石とされる「長期的な」「一貫性のある」アプローチも疑わしく思えてくる。
頑なに「ガンバのサッカーとは〇〇」と固定するのは未来の可能性を狭めるリスクも伴う中で、松田さん退任人事は別れへの寂しさはありつつも、仕方ない側面もあると捉えている。監督人事や選手の編成から垣間見えてくるだろうチームの新指標はガンバをどんなチームに変えるだろうか。
欧州移籍だけが目指すべきキャリアなのか?
そんな不安定な評価に人生を大きく揺さぶられるのがサッカー選手のキャリア。「〇〇チルドレン」に代表される監督との出会いに恵まれる選手がいれば、パフォーマンスに見合わない出場機会しか得られない選手もいる。
コントロールできない要素も多いキャリアに対して、10代後半~20代前半の選手たちがこぞって欧州移籍を前提とした『ステップアップ至上主義』のような考え方をしていることに少し心配なる。
宇佐美貴史選手も若い時はバロンドールを目標に掲げていた時期があったし、そうした目標からの逆算をふまえつつ彼らは「欧州では自分は若くない」といった趣旨の言葉を口にする。日⇆欧の移籍活性化が目的の1つだとされる秋春制の導入でこのトレンドはしばらく続くことが予想される。
メディアがステップアップを煽る影響もあるのだろう。今シーズン大きな期待とともにガンバ大阪に加入しつつも、満足な出場機会を得られていない名和田我空選手に関する報道は特に顕著。その多くが行間に『想像していたキャリアとのギャップ』を滲ませる内容になっている。
向上心がストイックさと紐づくのは言わずもがな。『倉田塾で筋トレ頑張っています』『アヤックスでの練習参加で危機感が生まれた』……名和田選手に関して目にする情報はどれも真面目。余計なお世話ながら、ワーク・ライフ・バランスは大丈夫だろうか。
個人的には「遠藤コーチがオフに競馬場に連れて行ってくれました」みたいなエピソードも聞きたいし、「マスカレードボールみたいに僕もキャリアの最後に差し切ればいいなと思いました。今は脚をためます」くらいの発言(余裕)があってもいいと思う。コーチから学べるのは技術だけではない。
現在は解説者として活躍する内田篤人さんや中村憲剛さん、ミチ(安田理大)もそうだが、コメントに説得力があるのは苦労していた時期の経験談。今は日本代表として活躍する中村敬斗選手も1年目は苦労した。名和田我空選手の今シーズンを評価するのはもう少し先でいい。

今後の飛躍が期待される名和田我空選手
そもそも欧州移籍以外にも素晴らしいキャリアが積めるルートはたくさんある。
例えば、柏木陽介さんは規律違反でレッズを退団した後に所属したFC岐阜で、引退後の「鵜飼観覧船の船頭」挑戦に繋がる出会いがあった。このセカンドキャリアは大きな話題になったし、岐阜をPRする柏木さんの姿には現役時代とは違った魅力を感じる。
そうした偶然性もキャリアの醍醐味。サッカー選手としては最高峰の舞台ではないかもしれないが、それぞれの立場や環境で挑戦を続ける物語に勇気づけられることは多々ある。
納得のいかない評価で遠回りさせてられたと思っていたキャリアが、意外な出会いや才能の気付きをもたらしてくれることもあるだろう。だから、自分にも言い聞かす。不遇を託つ前に現状を再評価しよう。その姿勢が未来をより良いものにするはずだと。
Photos:おとがみ