フットボールチャンネルに小幡真一郎さんのインタビュー記事「ストイコビッチにイエローカードを出された審判 -小幡真一郎インタビュー-」を寄稿した。
ストイコビッチにイエローカードを出された審判 -小幡真一郎インタビュー-https://t.co/TOcJGpCN8U
(取材・文:玉利剛一 @7additionaltime )— フットボールチャンネル⚽️ (@foot_ch) 2018年11月24日
小幡さんとは筑波大学大学院で共にスポーツを学ぶ“同級生”という間柄である。30歳以上年齢の違う私たちが、同じ教室で学ぶ環境は大学院の面白いところ。授業以上に小幡さんをはじめ、スポーツ界で活躍する同級生との会話は自身の学びとなっている。
……と言いながら、実は入学するまで小幡さんの存在を知らなかったことを正直に告白しなければならない。入学式で小幡さんの「サッカーの審判と教師をやってました」という自己紹介を「へぇ」と受け流したことを今は反省している。入学式の帰り道、グーグルで「小幡真一郎」と検索して表示された情報を見た時の驚きは忘れない。
「1993年Jリーグ開幕戦の主審を担当」「ストイコビッチにイエローカードを出された審判」など私が少年時代、夢中でJリーグを観ていた頃に起きた印象的な出来事の張本人だったのだ。以降、私の“レジェンド”に対する態度が変わったのは言うまでもない。
今回のインタビュー記事は、授業後にいつも立ち寄るお好み焼き屋「和」での会話がベースになっている。Jリーグ審判に関する情報はクローズドの部分も多い中で、小幡さんの現役時代の経験や、指導者の立場から考える“審判論”は間違いなく面白い記事になる確信があった。
取材にあたっては、1993年のJリーグ開幕戦で着用したユニホームを準備いただいたり、記憶を思い返してもらうために当時の試合映像を見てもらったり、諸々の準備・協力いただいた小幡さんはもちろん、本企画を許諾いただいたJFA様にもあらためて感謝したい。
反響を受けて
記事タイトルはインパクトを重視して「ストイコビッチにイエローカードを出された審判」とした(ちなみに、ボツになった候補タイトルは「審判はつらいよ」「たとえ批判されようとも」)。伝えたかったのは、小幡さんの経験談を通じた審判への正しい理解。反響を見聞きする限り、その目的はある程度果たせたと考えている。
見出しは地味だが、日本サッカーにおける審判のきつい立ち位置や育成の必要性など見どころだらけの濃いインタビューだ…。|ストイコビッチにイエローカードを出された審判 -小幡真一郎インタビュー-(フットボールチャンネル) – Yahoo!ニュース https://t.co/FPxQDdqRJA
— 🎋モト田中ベッチュー🎋 (@mototanaka) 2018年11月24日
インタビュアーの切り口も含めて本当に良いインタビューだと思う。自分も審判を批判しがちだが感謝し気を付けないとなと思った / “article?a=20181124-00010000-footballc-socc” https://t.co/pqlM3wEJy8
— 温玉屋 (@BoiledEgg1987) 2018年11月24日
フットボールチャンネルにしてはずいぶん良記事。おっしゃる通り、日本は審判への理解が低い。もっとフォーカス当ててリスペクトされるべき。
ストイコビッチにイエローカードを出された審判 -小幡真一郎インタビュー-(フットボールチャンネル) https://t.co/T6Tbj2etLm
— おかもとけいた (@okamoto_keita) 2018年11月24日
この記事が公開された直後にタイミングが良いのか悪いのか「柿沼主審騒動」が発生したことも多くの人に読まれる要因となった。この件に関しては擁護できない部分もあるが、柿沼主審に対して“下手くそな審判”というレッテルを貼って、今後のレフリングの批評をしないように心掛けるつもりである。第2の家本主審のような被害者を生みたくないという想いも、今回の記事を書いた理由の1つだからだ。
おわりに
取材前に「引退してかなりの時間が経った審判のインタビューなんて読んでくれる人いますかね?」と不安を口にしていた小幡さんから「(記事を読んだ)教え子から連絡がきました」と報告を受けた時は嬉しかった。お好み焼屋で審判論を語る小幡さんの姿から、私は小幡さんをまだ“現役”だと捉えている。小幡さんの審判に関する豊富な経験と深い(熱い)考えは色褪せない。微力ながら、この記事を通じて小幡さんの再評価に貢献できたのなら嬉しい。小幡さん、今後とも宜しくお願いします。
※小幡さんは今年ブログ「17条とコモンセンス」を開設されました。こちらもご確認ください。
 Copyright protected by Digiprove
Copyright protected by Digiprove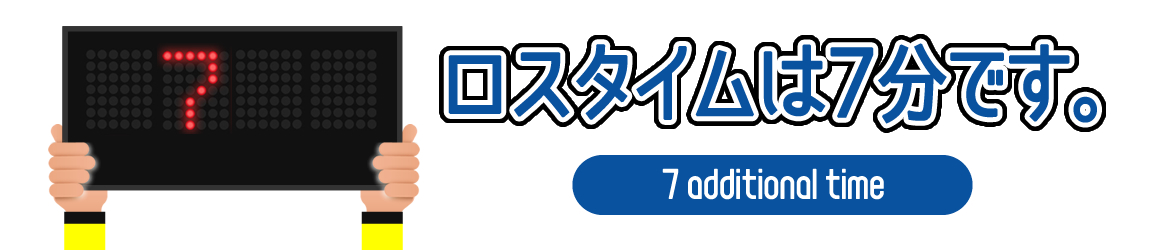



















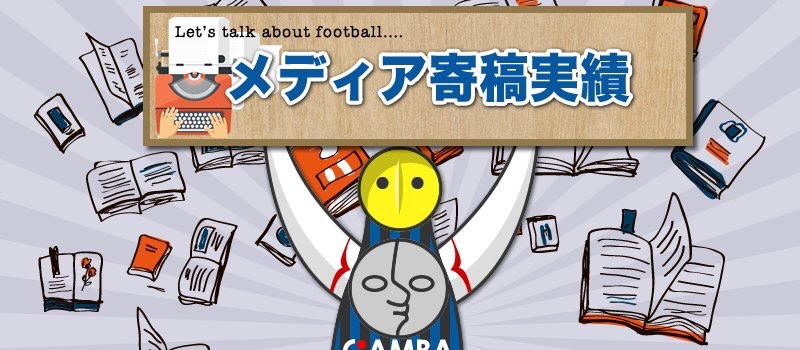

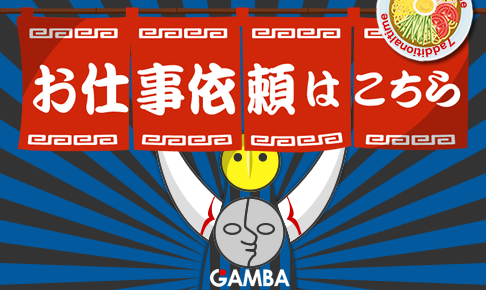

コメントを残す