先日、フットサル日本代表監督のブルーノ・ガルシア氏の講演会に参加した。氏は「パフォーマンス」を定義を【タレント×モチベーション】だとし、特に【モチベーション】の大切さを熱っぽく語った。ただ、それを高める方法については言及されず、
「フットサルに人生を捧げている選手が私のチームには必要だ」
「時には狂気的な野心が求められる」
など、熱い言葉を聞けば聞くほど、「高いモチベーションを持っていること自体がタレントでは?」という感想を持った。モチベーションを高めるのは簡単ではない。
小井土監督のマネジメント
その数日後、既述の懸念に対するアンサーになりうる話を教えてくれたのが、筑波大学蹴球部監督の小井土正亮氏(元ガンバ大阪アシスタントコーチ)である。
小井土氏のチームマネジメントは「一人一役」という筑波大学蹴球部の伝統をブラッシュアップさせる形で生まれたものだという。「プロモーションチーム」「パフォーマンス局」など、12のセクションを設け、更に各セクション内でも「ファンクラブ担当」「ビデオエディット担当」と役割を細分化している点がポイントだ。
部員全員に明確な担当を持たせることで、大人数が所属する組織のパワーをチームに反映できると共に、試合への出場機会がない選手もチームへの貢献を実感できる仕組みになっている。
経験的には、チーム(モチベーション)マネジメントの肝は“相手に信頼を示す”ことだと考えている。責任あるミッションを任せることで、相手はその決断を粋に感じ、任せてくれた相手や組織のために貢献する意識が芽生える。やらされている意識がないので、言動には自主性が伴い、組織に多様性も与える。
そもそも【監督】を意味する「COACH(コーチ)」とは、四輪馬車が語源。つまり、乗客を目的地まで運ぶのが役割であり、運転手が目的地を決めることはできないのである。筑波大学蹴球部の組織マネジメントの話からは、小井土氏がチームが勝つこと以外に、人間的成長も目的としており、教育者としての顔もあることを感じた。
2つのアプローチ
チームマネジメント術に関しては、大きく2つのアプローチが議論されることが多い。自主性を促す「コーチング」と、戦術の実践(遵守)を求める「ティーチング」だ。歴代のガンバ大阪監督においても、両方のタイプが存在した。分かりやすいところで言えば、西野監督は前者、長谷川監督は後者だろう。クルピ監督は前者だと思うが、正直よく分からない。
では、宮本恒靖監督はどうか。
選手のコメントから推測するに、スクランブル登板した2018シーズンは“無”(クルピ監督時代の借金)であったピッチ上の規律を「ティーチング」で整理するアプローチだった。残留のためにはその選択肢しかなかったともいえる。
では、準備する時間を与えられた今シーズンのマネジメントは……。
小井土さんは、自主性を尊重するマネジメントについて「自分で考えることができる筑波大学の学生だからこそ(実現できた)」と語る。ガンバで成功した西野監督のマネジメントが、名古屋グランパスやヴィッセル神戸では成功しなかったように、チームとの相性は存在する。正解がある類のものでもない。近年は主流派になりつつあるように感じる「コーチング」が必ずしも正しいとは言い切れない。
昨シーズンの結果を宮本監督がどのように捉え、選手達に働きかけていくのか。今シーズンもメディア情報の行間を読みながら、チームマネジメントにも注目したい。
 Copyright protected by Digiprove
Copyright protected by Digiprove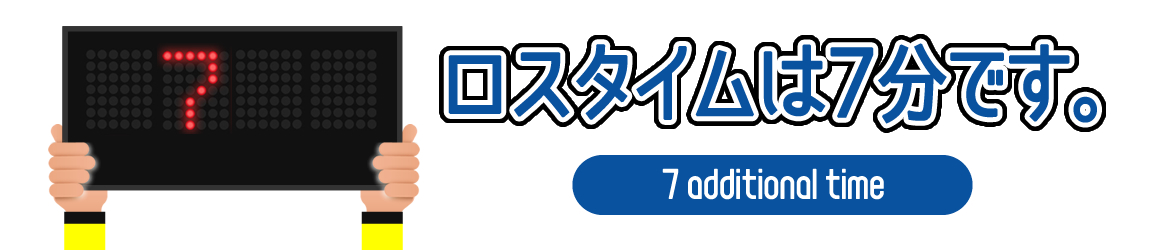







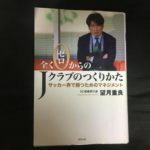
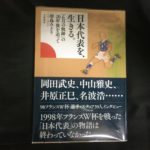






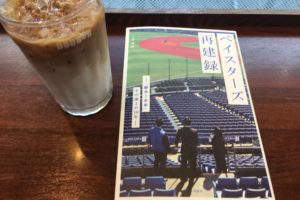







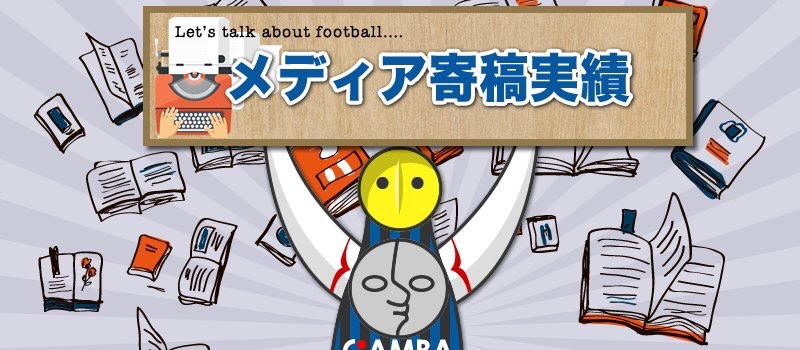

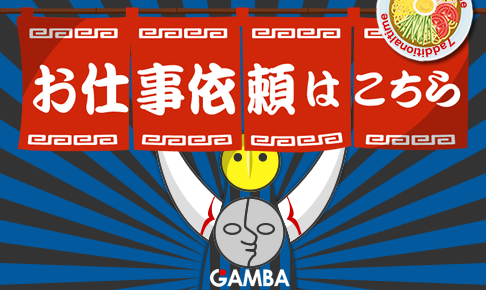

コメントを残す