ガンバ大阪オフィシャルマガジンで、倉田選手がクルピについてこんなことを語っていた。
とにかく、決め事が少ない。実際、監督も「A選手がここに動いたら、B選手はここに動け」というような、固定した選出は決めたくないとおっしゃっていて。
クルピのサッカーには、細かい戦術が存在しない。選手のイマジネーションに期待する、芸術性の高いサッカーを志している。聞こえはいい。しかし、「自由」は諸刃の剣だ。似たようなチームマネジメントだったジーコジャパンが、最後まで一体感を持てなかったように、扱いが難しい代物である。
特にガンバ大阪は昨年まで逆のマネジメントをする指揮官に率いられてきた。同じくガンバ大阪オフィシャルマガジンで、山口智コーチが「指示待ちの選手が多い」「自分達がどうしたらいいのか発信できない」と、選手に対して苦言を呈していたが、自由に慣れるまでに時間がかかるのは仕方ない側面もある。クルピのマネジメントは、今のガンバにとっては劇薬だったということか。副作用が想像以上に大きかった。
実はゴール裏(サポーター)の世界でも同じようなことが起きている。「もっと声を出せ!飛び跳ねろ!」「手拍子は頭の上!」と、応援を強要するサポーター団体のことが嫌いな人も、不祥事でこれまで応援をリードしていたサポーター団体が解散した後、応援の熱量が物足りない現実に直面し、過去の強要が恋しくなっている言動をたびたび目にする。今冬に訪問したバルセロナの応援はとても自由な雰囲気で驚いたが、選手もサポーターも、まだそこまでのレベルに至っていないということなのだろう。
岡田メソッドから学ぶ
歴史を振り返ると、あのナチスでさえ、支持者が存在したという事実。自由を重荷と感じ、何かで自分を拘束したいと考える人もいる。それは決してマイノリティな存在ではない。
そう考えると、岡田武史氏がFC今治で提唱する「岡田メソッド」は参考になる。守破離。チームとして前提の共通認識となる(戦術の)「型(KATA)」を設けた上で、その延長線上に自由を与えるアプローチ(と理解している)。“いきなり自由”ではない点が、日本人と相性が良さそうだ。
クルピは「型」をまずチームに浸透させるマネジメントを検討しないのだろうか。少なくとも、現状のままでは非常にマズい。クルピに期待できないのであれば、コーチであるツネ様や智さんに期待したい。西野朗監督時代のガンバは、クルピに近い(自由を尊重する)マネジメントが行われていたと聞く。その(自由マネジメントの)成功体験を持つ2人がコーチとして在籍していることが、現時点での数少ない希望である。
だけど……あぁ、自由なんていらない。
 Copyright protected by Digiprove
Copyright protected by Digiprove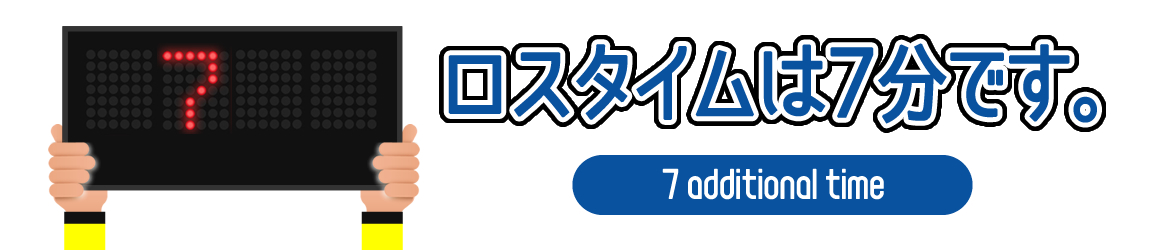
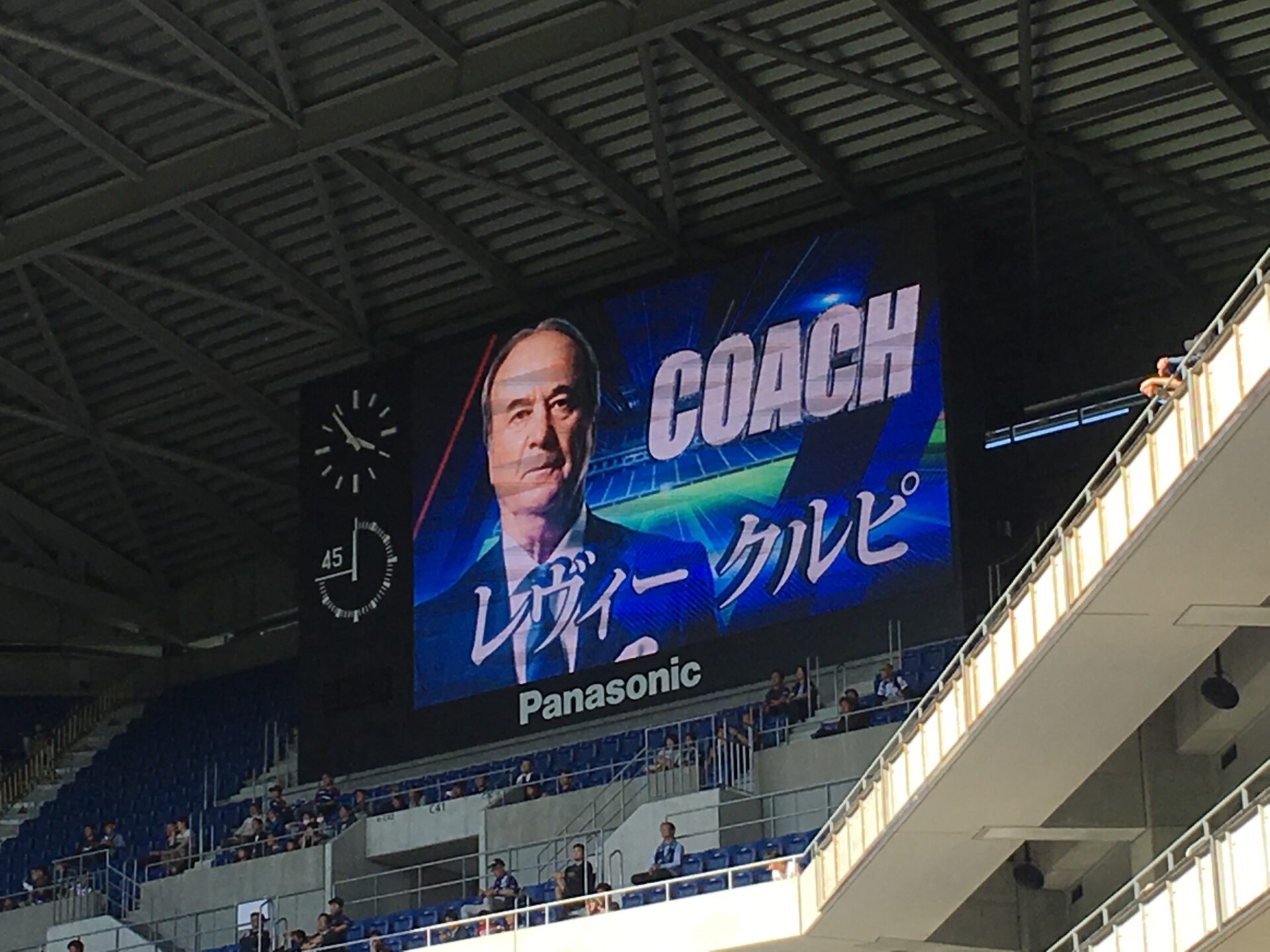


















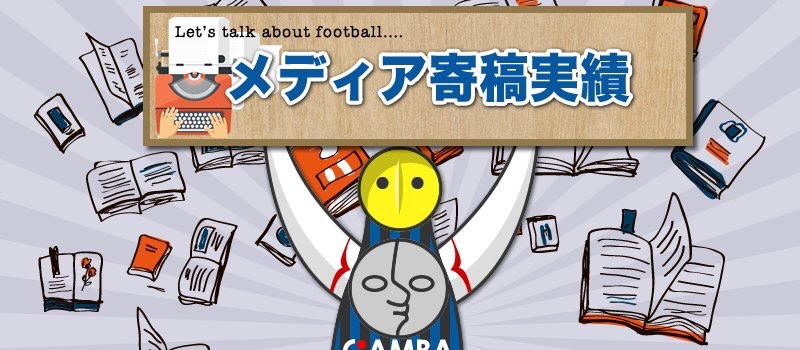

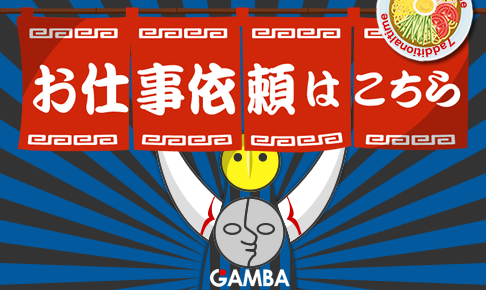

コメントを残す