平昌五輪の開幕を機に、五輪について理解を深めたいと思った購入した一冊。
13年もかかったという長野五輪の開催に至る道筋を、そもそもの発端から解き明かし、大イベントに振り回される地方自治体と地域住民の笑えない実体をつぶさに描き出す。
プロローグに記載された内容通りの内容となっている。扱うテーマは1998年に開催された「長野冬季五輪」。五輪招致のきっかけとなった信濃毎日新聞記者取材の会合から物語が始まる。そこから……
- 長野市と松本市の対立を背景としたマスコミによる県民世論の誘導
- 五輪反対派議員・今井寿一氏への圧力
- 長野市独特のピラミッド型自治体組織「区長会」制度の利用
- JOCと長野市による大会組織委員会ポストを巡る争い
- 「ホワイトスノー作戦」による外国人労働者の取り締まり強化
- “一店一国運動”“五輪協力会”“公務員のボランティア”など半強制的な県民稼働
など、あまり報道されない(表に出てこない)出来事が批判的な目線と共に紹介されている。“官主導の五輪”であることを証明する出来事が多々紹介されているが、読む進めるにつれて「五輪は誰のもの?」という問いが自分の中で大きくなった。
書籍概要
書籍名:長野オリンピック騒動記
著者:相川俊英
発行:株式会社草思社
価格:1,600円(税別)
詳細はこちら

一校一国運動
そんな“官主導”の五輪の中で、信濃教育委員会が中心となって実施された「一校一国運動」について紹介された章が面白かった。学校ごとに応援する国をひとつ決め、学習、交流する。スポーツをきっかけとし、異国の文化や現状を知るのは私も何度も経験したことである。中にはこの運動をきっかけに交換留学をするまで関係を発展させて事例もあるらしい(古里小学校×韓国)。この活動の提案者である「長野国際親善クラブ」の小出博治氏は書籍の中でこう語っている。
「子供たちは言葉が分からなくても、外国の人と接して、楽しんでいる。交流というのは、言葉が先行するものではない。言葉が通じなくても、相手を知って、楽しく付き合えば、小音は通じる」
2020年には東京五輪も控えているが、この活動は継続するのだろうか。東京五輪のレガシーの1つとして子供達が特別な経験ができれば素晴らしいことだ。
まとめ
ここまで緻密な取材でもって出版されたスポーツドキュメンタリー本は(発行年は前後するが)「争うは本意ならねど」以来。
次々に明らかになる事実は山崎豊子の小説を読んでいるような重厚感。特に五輪の国内候補地決定投票において西武・堤義明氏が政治力を発揮するくだりはTBS日曜劇場化まったなし。政治と金。五輪の闇を知るにはぴったりの一冊。
 Copyright protected by Digiprove
Copyright protected by Digiprove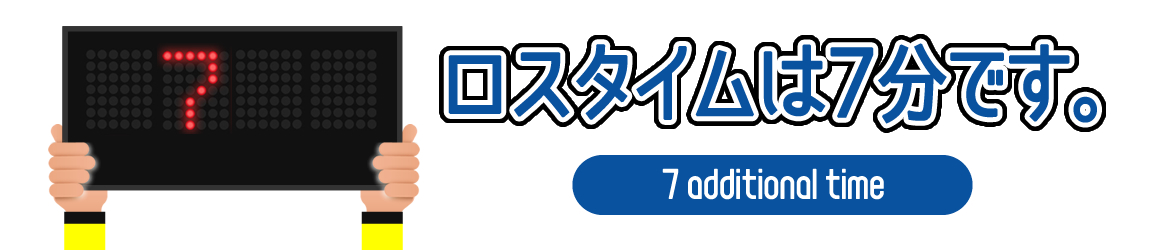
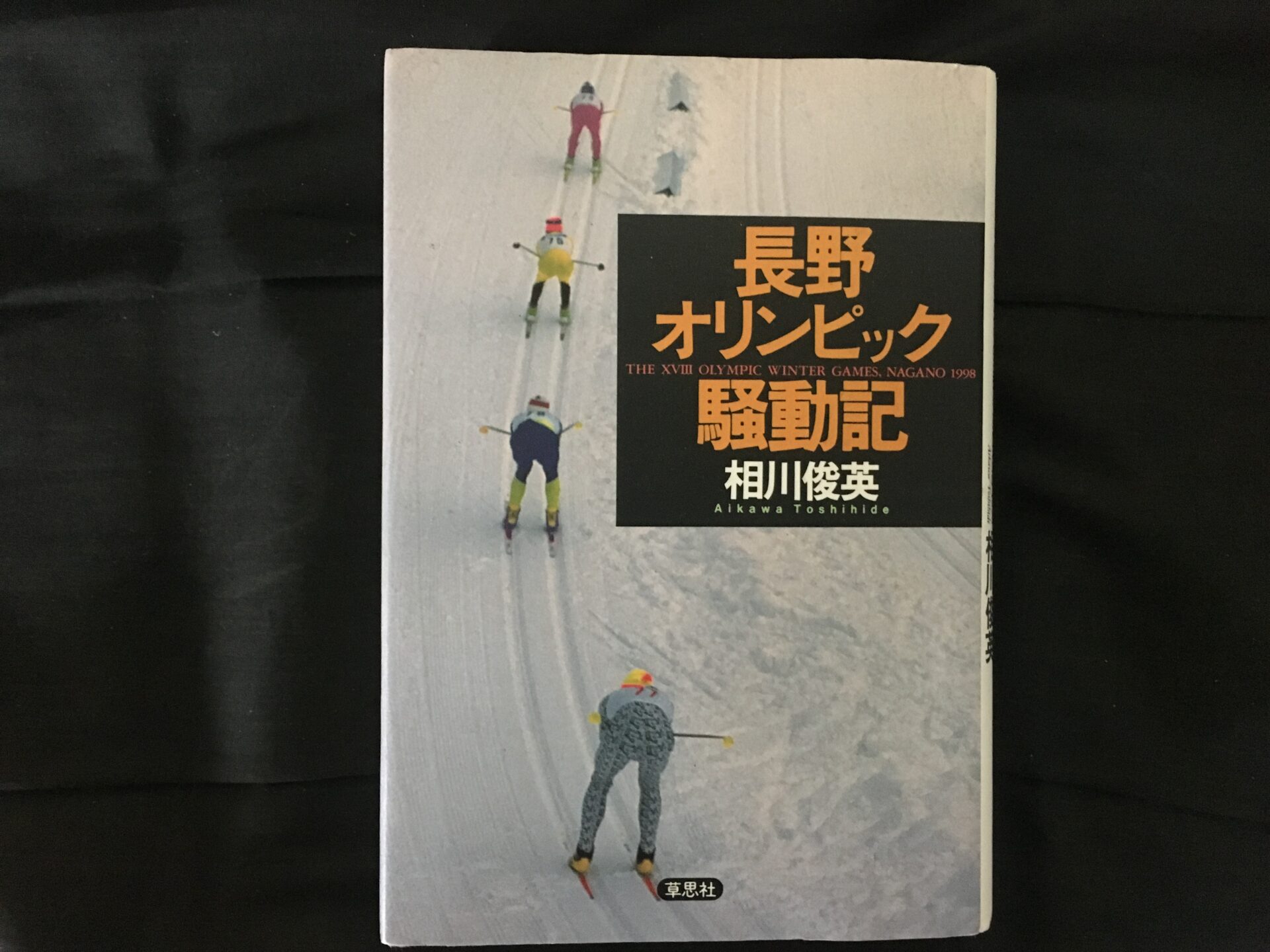




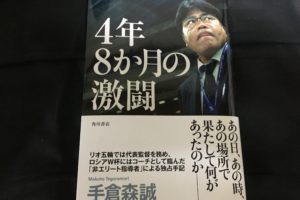
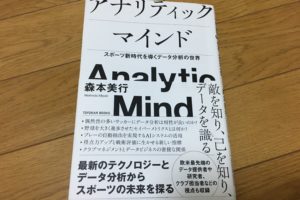
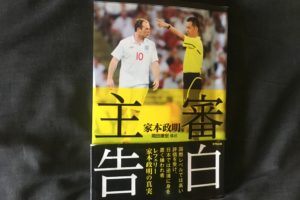
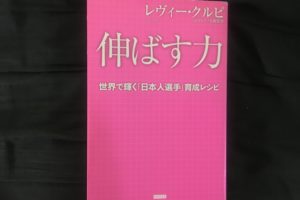
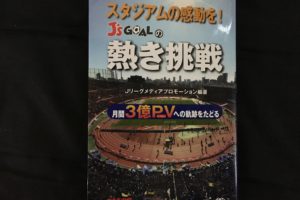

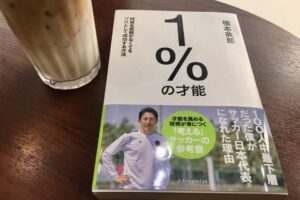
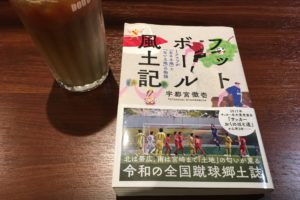






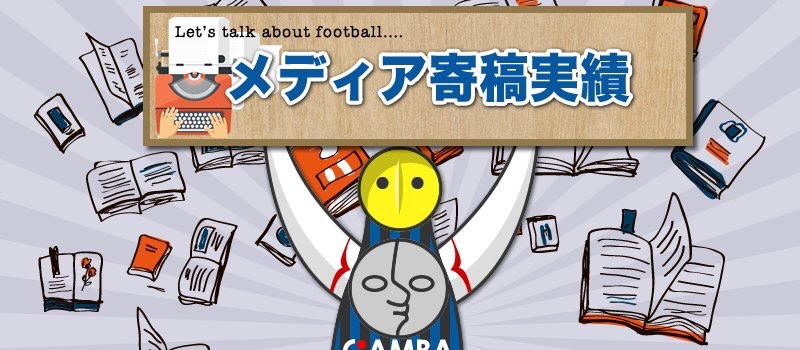

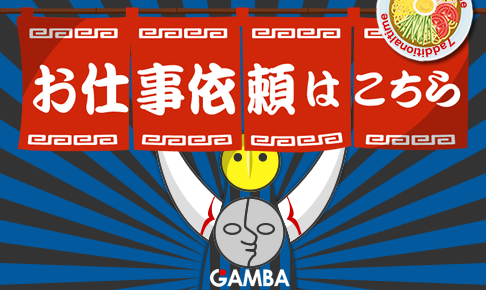

コメントを残す